
マノエル・ド・オリヴェイラ(1908〜)
「運命の力は大きい。泉は大河になり、大河は個性を持つが、それが海に注ぐときその個性は完全に失われます。
それは私が絶対と呼ぶもので、つまり大河は絶対に流れ込むのです。この絶対は蒸発して雨に変わり、雨は泉を生み出す。
これがひとつのサイクルです」―プレス、インタビューより
暗闇に鋭く差し込むような光線が当てられ、その部分を強調すると同時に暗闇の部分を逆に強調する、そんなレンブラントの絵画。
オリヴェイラの画面が絵画のように審美的なだけでなく、観ている人に明るさよりも暗さを見せるのであれば、これもまた一つのサイクルだ、などと思ってしまう。世界最高齢の映画作家として前人未到の地平で撮られた映画は、太刀打ちできないほどの強度を私たちの前に出現させる。
「この映画のテーマは『貧困と名誉』。政治的なメッセージに直接結びつくものではないが、もちろんそれを見出すことはできます。
私が脚色したテキストは20世紀初めのものですが、映画は21世紀初めに作ったもので、ふたつは現代性という点でつながっているのです」 ―プレス、インタビューより
この作品の背景に、ポルトガル大航海時代の豊かさは見ることはできない。それでは何がここに存在するのか。ドア、ランプ、 帳簿、鍵、コーヒー、父、母、息子、嫁。ただ交わされる会話の中にひたすら起ち上がってくる貧しさと生産性のない繰り返し。いつしか母は嫁を憎み、息子を偏愛する。父は嫁を慈しみ、嘘をつく。ドアの向こうには聞き耳がたてられているかのように思われ、「7たす7は14、さらに7たすと21」と足し算ばかりを記入する帳簿は、遠い異国で作られたコーヒーを手に入れるため(お金を稼ぐため)だけではなく、結果的に(金庫の)鍵を破り去ってしまう。ランプはその姿を隠す暗闇も作り出すのだ。慎ましく暮らす家族の姿から起ち上がってくるものは、幸せとは程遠い、悪循環の掛け算にも見える。しかし、それもまたランプが見せた闇の側面にすぎない。もし言い過ぎてしまってもいいのであれば、明るい時代にこの映画を見ることができない不幸をオリヴェイラは現代性と呼ぶのだと、この監督の厳しくもあたたかな、そして冷徹にして透明な視線に戦慄さえ憶えるのだ。
テオ・アンゲロプロス(1935〜2012)
「何も終わってない。終わるものはない。帰るのだ」
『エレニの帰郷』はテオ・アンゲロプロス自ら「20世紀三部作」と名付けて構想された2作目。オデッサを追われたギリシャ難民がギリシャに到着するシーンから始まる一作目『エレニの旅』のはじまりに対し、ローマのチネチッタ撮影所の門をくぐる映画監督A(ウィレム・デフォー)のモノローグから始まる。
テオ・アンゲロプロスがフレームの外に語りかけるとき、その先にはいつも彼の視線を待ち続けている人々がいた。ゆっくりと時を刻むように一定の速度で横移動するカメラが、あるいは対象を円形の動きで追いかけるとき、そのフレームを抜き去って遠くへ行ってしまう者、追いつくことができずに二度と目の前に姿を現さない者がいた。そこにはいつでも、待つものと待たれるものの諦めがたい気持ちが衝突する、時を越えたいくつもの出会いがあった。
「現在の時間と過去の時間は
おそらく共に未来の時間の中に現在し
未来の時間はまた過去の時間の中に含まれる」 ―T・S・エリオット『四つの四重奏』の第1部「バーント・ノートン」冒頭より
アンゲロプロスがたびたび引用していたという詩を読むとき、どこか難解なイメージのあるアンゲロプロスの、ある意味では愚直と言っていいほどにまっすぐなあのまなざしを思い出さずにはいられない。1900年の始まりを描いた『アレクサンダー大王』から、1999年の終わりを描く『エレニの帰郷』まで。それは、歴史の交錯する一点を映像で描く叙事詩人という映画史にも類まれな20世紀の大作家の、「ギリシャの現代史三部作」の『1936年の日々』から一貫して変わらないスタイルだ。
歴史の権力的な視点から、生き証人とも言える人々の個人史を描くことに移行していったアンゲロプロス。しかも、今回はギリシャを離れ、ローマ、北カザフスタン、シベリア、ニューヨーク、トロント、ベルリンと、故郷に帰ることもできずに世界中の時の場所で何度も出会っては別れるエレニ(イレーヌ・ジャコブ)とスピロス(ミシェル・ピコリ)の2人の愛の物語を描いた。そして自分の国に帰ることなく、エレニを見守り続けて生きてきたヤコブ(ブルーノ・ガンツ)もまた、私たちに人を愛することの忘れられない姿を残すだろう。過酷にして得難い人生の軌跡。この感動の先に、どんな映画をアンゲロプロスは考えていたのだろうか。
「時の埃はすべてに降りかかる。大きいものにも、小さいものにも」
台詞がいやに耳に残る。
(ぽっけ)
家族の灯り
GEBO ET L'OMBRE
(2012年 ポルトガル/フランス 91分  ビスタ/SRD)
ビスタ/SRD)
 2014年8月2日から8月8日まで上映
■監督・脚本 マノエル・ド・オリヴェイラ
2014年8月2日から8月8日まで上映
■監督・脚本 マノエル・ド・オリヴェイラ
■原作戯曲 ラウル・ブランダン
■撮影 レナート・ベルタ
■編集 ヴァレリー・ロワズルー
■出演 ジャンヌ・モロー/クラウディア・カルディナーレ/マイケル・ロンズデール/リカルド・トレパ/レオノール・シルヴェイラ/ルイス・ミゲル・シントラ
![]()
 ある街で帳簿係として働くジェポは、妻ドロテイアと義理の娘ソフィアとともにつましく暮らしている。彼らの息子ジョアンは8年前に忽然と姿を消していた。ジェポは息子の失踪した秘密を知っているが家族には隠していた。ジョアンの帰りを待ちわび、悲しみにくれる日々を過ごす一家。そんなある日、突然ジョアンが帰ってきた…。
ある街で帳簿係として働くジェポは、妻ドロテイアと義理の娘ソフィアとともにつましく暮らしている。彼らの息子ジョアンは8年前に忽然と姿を消していた。ジェポは息子の失踪した秘密を知っているが家族には隠していた。ジョアンの帰りを待ちわび、悲しみにくれる日々を過ごす一家。そんなある日、突然ジョアンが帰ってきた…。
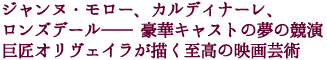
 現在105歳、現役最高齢の劇映画監督であるポルトガルの巨匠マノエル・ド・オリヴェイラ。90歳を超えてからも尚、毎年1本という驚異的なペースで新作を発表し続け、その作品は老いや衰えを感じさせることなく、むしろ映画へのさらなる情熱や瑞々しさを感じさせる。待望の新作となる『家族の灯り』はポルトガルの作家ラウル・ブランダンの戯曲を映画に翻案、オリヴェイラ自身が脚本を担当した。
現在105歳、現役最高齢の劇映画監督であるポルトガルの巨匠マノエル・ド・オリヴェイラ。90歳を超えてからも尚、毎年1本という驚異的なペースで新作を発表し続け、その作品は老いや衰えを感じさせることなく、むしろ映画へのさらなる情熱や瑞々しさを感じさせる。待望の新作となる『家族の灯り』はポルトガルの作家ラウル・ブランダンの戯曲を映画に翻案、オリヴェイラ自身が脚本を担当した。
 出演はジャンヌ・モロー、クラウディア・カルディナーレ、マイケル・ロンズデールら豪華俳優陣。失踪した息子を盲目的な愛で信じ続ける母、置き去りにされ悲しみの中で毎日を過ごす息子の妻、人生と社会に抗い、家族を捨てた息子、そして家族を守り、最後に大きな決断をする実直な父――物語の大半が家族の住む家で繰り広げられる本作は、どこにでもある家族の愛の姿を、オリヴェイラならではの厳しくもやさしい視点で描き、崇高な芸術にまで高めている。
出演はジャンヌ・モロー、クラウディア・カルディナーレ、マイケル・ロンズデールら豪華俳優陣。失踪した息子を盲目的な愛で信じ続ける母、置き去りにされ悲しみの中で毎日を過ごす息子の妻、人生と社会に抗い、家族を捨てた息子、そして家族を守り、最後に大きな決断をする実直な父――物語の大半が家族の住む家で繰り広げられる本作は、どこにでもある家族の愛の姿を、オリヴェイラならではの厳しくもやさしい視点で描き、崇高な芸術にまで高めている。

エレニの帰郷
TRILOGIA II: I SKONI TOU HRONOU
(2008年 ギリシャ/ドイツ/カナダ/ロシア 127分 
![]() ビスタ)
ビスタ)
 2014年8月2日から8月8日まで上映
■監督・脚本 テオ・アンゲロプロス
2014年8月2日から8月8日まで上映
■監督・脚本 テオ・アンゲロプロス
■脚本協力 トニーノ・グエッラ/ペトロス・マルカリス
■撮影 アンドレアス・シナノス
■音楽 エレニ・カラインドルー
■出演 ウィレム・デフォー/ブルーノ・ガンツ/ミシェル・ピッコリ/イレーヌ・ジャコブ/クリスティアーネ・パウル
![]()
20世紀末の現在。ローマの撮影所チネチッタに映画監督Aがやってくる。彼は、ある理由により中断した撮影を再開しようとしていた。ベルリンを舞台に、歴史的事件と彼の両親のパーソナルな人生との関係を描こうとするその作品の完成は困難を極めていた――。
 如何なる苦境に陥っても、それでも人は希望を求め、愛する人のもとへと帰郷する――これは、抑圧と動乱の20世紀を生きたエレニという女性、そして彼女を愛しつづけた男と、彼女が想いつづけた男の物語だ。ローマ、北カザフスタン、シベリア、ニューヨーク、トロント、ベルリンなどを舞台に「時の塵」(原題“The Dust of Time”)が誰にも等しく降り注ぐ。情熱と孤独に引き裂かれたエレニの姿が詩情あふれるダイナミックな映像によって描かれる。
如何なる苦境に陥っても、それでも人は希望を求め、愛する人のもとへと帰郷する――これは、抑圧と動乱の20世紀を生きたエレニという女性、そして彼女を愛しつづけた男と、彼女が想いつづけた男の物語だ。ローマ、北カザフスタン、シベリア、ニューヨーク、トロント、ベルリンなどを舞台に「時の塵」(原題“The Dust of Time”)が誰にも等しく降り注ぐ。情熱と孤独に引き裂かれたエレニの姿が詩情あふれるダイナミックな映像によって描かれる。
![]()
2012年1月24日、撮影中の事故により惜しまれつつ急逝したテオ・アンゲロプロス。『旅芸人の記録』や『霧の中の風景』など数々の代表作によって世界的巨匠となった彼が、最後に自ら完成させたのが『エレニの帰郷』である。前作『エレニの旅』に続き、20世紀を主題とした三部作(トリロジア)の中核として撮り上げた作品でもあり、歴史に翻弄される3人の男女の姿、その愛の激しさが描かれている。
主人公エレニを『ふたりのベロニカ』のイレーヌ・ジャコブ、エレニの息子であり、アンゲロプロス自らの姿が投影されたかのような映画監督Aを『アンチ・クライスト』のウィレム・デフォーが演じ、また、ブルーノ・ガンツ、ミシェル・ピッコリら豪華キャストが集結。ギリシャ古典悲劇の格調と現代史の騒乱が奇跡的に共存した傑作。時を超えた壮大な愛の叙事詩が幕を開ける。
