
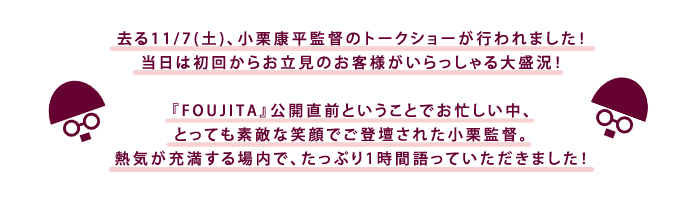
司会:今回の小栗監督全作品上映は、11/14(土)より公開となります、小栗監督10年ぶりの新作『FOUJITA』の公開を記念しての特集となります。ですので、本日は新作『FOUJITA』についてもじっくりお話をお聞きしたいと思っております。まずは、なぜ今回、藤田嗣治を題材に選んだのでしょうか?
監督:直接のきっかけはお誘いを受けたところから始まったんですけど、調べてみるとこれはオレの仕事だ、と(笑) 僕は1945年の生まれで、今日最初に観ていただいた『泥の河』が35歳のときの映画ですので、折り返してちょうど藤田に行きついたということですね。
僕は直接戦争を経験していないんですけれど、戦後に生れた者として、日本人とはなにか、自分自身とはどんな時代にどういった自己形成をしてきたのか、ということが映画を作る上での基本的な問いとしてあって。そうやって三本(『泥の河』、『伽倻子のために』、『死の棘』)、戦後の問題を自分なりに捉えてきて、今度の『FOUJITA』ではもう一回り大きく、戦後70年の問題だけではなくて、明治以降に日本が受容してきたヨーロッパ近代というものが、いま我々にどういう形で花開き、どんな歪みを残し続けているのかということを、藤田嗣治を通して見たいと思ったんです。
藤田は20年代のエコール・ド・パリで寵児と騒がれて、想像を絶するほど売れた人です。浮世絵の本当に美しい白で裸婦を描いて、戦時に日本に戻ってきてからは、日本画的な裸婦とは全く違う、ドラクロワみたいな西洋絵画の伝統的な歴史画を描いた。今こそ日本の油絵として自分は描ける、そういう歴史画を描くんだ、と。「アッツ島玉砕」を始め、藤田が描いた戦争協力画が果たした役割は複雑ですが、時代と表現者との関係や、20年代と40年代、パリの市民社会と日本の急ごしらえの近代国民国家としての様相など、藤田が跨いだ溝というのはとても大きいものがあったと思うんですね。それを2015年の今改めて照らし直す。ですから、戦争のことでもあるんですが、もう少し近代というような枠組みまで問題を広げて捉え直そう、というような仕事になったと思っています。
司会:藤田嗣治の絵は元々ご覧になっていたのでしょうか?
監督:特に好きな人ではなかったんですけど(笑) 騒がしいエピソードの多い人でしたよね。そういうのも含めて、ごく一般的な藤田像しか知らなかったんです。絵を見て好きになったというか、例えばパリの近代市立美術館で、同時代の人と藤田の裸婦像を並べて見ると、同じ油絵でも藤田のは全く違う。本当に美しい白です。江戸末期まで油画は日本社会にはなかったわけだから、これを明治19年生まれの藤田が学び、日本人としての技法・感覚を油絵の伝統に持ち込んで、パリで売れるまでになったというのはやっぱりすごいことです。良い絵というものは独特の静けさを持っていますから、藤田の絵もそうで、騒がしいエピソードではなくて、絵が持っている静けさから映画を作りたいと思った。そうやって段々引き込まれていったんです。
司会:同じ芸術として、絵画と映画の共通点など、監督が思っていることはありますか?
監督:藤田と僕はもちろん一緒ではないです。あんなに儲かったことはありませんし、褒められたこともない(笑) 絵画はキャンバスというフレームで、二次元に置き換えられた空間をそこに作り出すわけですよね。映画も同じなんです。現実は三次元で、広いフレームで見ているわけだけれど、映画っていうのはどんなにワイドで撮っても、ある意味でキャンバスと同じように切り取られている。そしてただ切り取るのではなくて、どこに何を置いて、どういう光のもとに、どういう人物をどう置いてというふうに、具体的に一つ一つ置き直していく作業が、映画では大事なことになってくる。その作業って絵を描くのとほとんど同じだと思うんです。つまり新しい空間の中に、事物を置き直すということです。

司会:過去に戦後三部作『泥の河』『伽倻子のために』『死の棘』を撮ってらっしゃいますが、戦後の日本の風景というのは監督の、どのようなこだわりがあったのでしょうか?
監督:三作とも高度経済成長前ですね。さっき言ったフレームの中に事物を置くという言い方でいくと、物の感触がまだ生きていた社会だった気がするんです。今はもう本当に大量生産・大量消費して捨て去られていく時代。例えば、お茶碗や箸のような手作りの物があったとすると、以前は、その物が生まれることになった自然に、物を通して至る道っていうのがあったはずなんですね。
ヒューマニズムっていうのは人を大事に、心を大事にしましょうねというふうにばっかり言うけれど、実は暮らしというのは心以上に物と触れていると思うんです。その触れる物がしっかりしているかどうか。多分それが高度成長以降の日本社会から奪われていって、いまやまともな映画は撮れないのではないかと絶望すら感じるほど、人と物とが切れているという感じがするんですね。例えばTPPという法律が成立し、強い経済だけが生き残るというふうに、物と個別に出会う道すら奪われていく。物が背後に持っている地域性、それが本当は命とつながっているはずなのに、いかにもグローバル、ユニバーサルだというふうに置き換えられて、数値化・情報化されて我々の生きていく実体がものすごく希薄になっていく。そこを映画はちゃんと描かなくてはいけないと思います。
司会:そういった地域性、物、あるいは風景を大切にするということから、そのあとのオリジナル脚本の作品につながっていったんでしょうか?
監督:そうですね。『眠る男』はそれまでの三本と違っていて、主人公が動かなくてしゃべらないので、物語のつくりようがないんですね(笑) この人間はなにを考えていて、どういう人間関係があって、何を良しとしているかというふうに、主たる映画の中に出てくる人物像を中心に語る。これは近代の人間を中心とした捉え方なんです。でも僕は、あまり心理として人物を描きたいとは思わない。むしろいつも人を中心にして描く映画のスタイルそのものが、「近代の自画像」みたいなものをちょっと信じすぎているんじゃないかと。そこから一回離れたいっていうのが『眠る男』でしたね。
今度の『FOUJITA』もある意味はそうで、伝記映画に全然なっていないんです。エピソードで人物を描くという手法は取っていなくて、20年代と40年代、パリと日本というのをただ並置して、その違いから観てください、と。物の映り方・見え方がどう違いますか、ということを、観て下さる方に預けるというようなやり方なんです。藤田という人物は、パリでさんざんいろんなことをしたけど、戦争が始まったらころっと手のひらを返して戦争協力画を描いたじゃないか、みたいな非常にステレオタイプで掴む人物像に対して、もうちょっと開きましょうよ、と。
例えば、パリならパリ、日本なら日本の田舎に人物を置いたときに、概念としてできあがっていた藤田像を、風景の中で解いていく。うまく言えないけれども、一人に集中していたことをみんなのものにしていくっていうんですかね、そういう方法が現代の映画には必要だと。それは、自分のことを振り返ってもそうで。1945年に生まれて、映画をやりたいと群馬から出てきて、早くこんな田舎から出て親父から逃げようとか(笑)、地域性とか風土性が自分の自由を奪うと思っていた。それがだんだんと、そんなことではないんじゃないかと気が付いた。ヨーロッパ近代だってひとつの地方にしか過ぎないのではないか。近代というものの考え方を相対化できるような、そういう手掛かりを我々は持てるようになってきたわけです。
難しいけれど、そこから先の映画は、人の起承転結だけで描くだけではだめだと。その起承転結の中心になる人物が、どれだけ深い孤独を、ヨーロッパ近代の自我というものを抱えているか。産業革命以降、人がどういうふうにバラバラになってきたか。つながることばかりを映画で求めてはだめで、バラバラになっているということをしっかりと見ないと。『FOUJITA』でそれがうまくいっているかわかりませんけど、思いはそうですね。

司会:日本とフランスの合作についてはいかがでしたか?
監督:むこうのスタッフとのコミュニケーションは問題ないです。労働時間とか賃金の問題っていうのは極端に違いますけど、それだけのことですからね。ただ、台詞がね。僕はシナリオを書く時に、できる限り台詞を約(つづ)めていきたいんです。日常ではべらべらと喋っても、せっかく映画という新しいフレームのなかに人物がいて、言葉が選ばれているわけですから。言葉がフレームの中を全部埋め尽くすんじゃなくて、少ない言葉がフレームの端に広がっていくようなイメージを持ちたいんです。その方が、台詞や言葉が複数の意味を持つようになる。
『FOUJITA』は、パリと日本、それぞれ1時間ずつという構成なので、映画の半分はフランス語なんです。だから僕の作った日本語をフランス語のダイアローグに置き換えてもらわなきゃいけない。そうすると僕が約めて書いた言葉を、むこうの方がどんどん伸ばすんでよ(笑) 「フランス語は会話を楽しむんだ。知的に表現を変えて、長く話すことが文化なんだ」と言うんですよね。もう、バンザイ(お手上げ)ですよ。
僕が書いたエッセイから「鐘が鳴っている」という一文を取りだして、これを翻訳してくださいと言うと、「誰が鐘を聞いてるんだ」「主語を明示しないと文章にならないだろう」と。でも、主語を明示した「俺が鐘の音を聞いている」と、「鐘の音が聞こえる」は別の表現ですよね。つまり、主語が特定される前に「鐘が鳴っている」という状態がある。ところがこれがフランス語にならんのです。フランス語だけじゃない、ヨーロッパ言語って必ず主語がある。そういう構文が頭のなかに組み立てられているわけだから、日本語表現の主語を隠すってことはありえないんですよね。でも我々はむしろ、共同体のなかで、俺が俺がという主語を隠しながら、コミュニケーションを探っていく。それは悪いことじゃないですよね。だって「鐘が鳴っている」っていう表現、美しいもの。それがむこうの文化には無いんです。
司会:まさに人中心なのか、物中心なのかということなんですね。
監督:そうです。あるいは状態が中心とか、そういうことです。それはおもしろいとは思うけど、理解はしにくいですよね。だから撮影中に、モニターがあるんですけど、むこうのスタッフが「まだ小栗は寄らないのか、どうしてカメラを動かさないんだ」と、そればっかり言うんです(笑) だって寄ったら場所がわかんなくなるでしょう、動いたら人間しか追いかけることにしかならなくなるでしょう(笑) そんなやり取りはよくありました。
司会:主演のオダギリさんにリクエストしたことはありましたか?
監督:独特な役者ですからね。『FOUJITA』みたいな映画の作り方にはとても合ってるタイプだと思います。場面場面で、藤田がどんな感情でいたかってところだけを、いつも掘り下げていきましょうというふうなやり方ですね。
この間のトークでオダギリ君が、「これまで自分はオダギリジョーだって、監督が何言ってもそれは俺に任せてくれっていう生意気を言い続けてきたけど、今回は監督に丸投げして結果は良かったです」って言っていて。半分はジョークでしょうけど。まあ、投げるっていうか、預けるってことですね。役者が監督に預けるってそれは当たり前だと思うかもしれないけど、全然そうじゃない。預けるって手を放すってことですからね、相手に。怖いですよ。でも映画って全部預けた結果なんですよ。役者だけじゃなくて、映画というのはすべて色んなものに預けているんだと思うんです。例えば、監督なんかは何もしてないわけですから(笑) 芝居するのは役者だし、山があれば、山は僕が作ったわけじゃないしね。当たり前ですけど、よーい、はい! ってキャメラを自分に向けることは絶対にないですよ。いつも視線を他者に向けてるんですね。他者から何かが立ち上がってくるのを撮りたい。映画っていう作業は集団でそういうことを預けっこする事なんだろうなって思いますね。
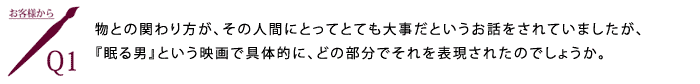
いくつかあるんですが、例えば、後半で眠る男が寝ていて、お母さんが昔の手紙を出してきて読む場面。お母さんが「お前はこんなことを考えていたんかい」と言って、外を見ると雪が降っている。お母さんの横にストーブがあって、眠る男の後ろには平松礼二さんが描いた、板戸の月と梅の絵がある。それが、窓外に雪が降る中、ストーブの赤い光を受けて、板戸の月が、ガラス戸のところにぼうっと大きさを変えて写るんですね。実際にはそうならないんですけど、ありえないわけではない。そういう画を作ることによって場の全体というのが全く違う感じになると僕は思ってるんです。そういうことって本当にいっぱいあると思うんです。それを撮りながら探してるという気がしています。
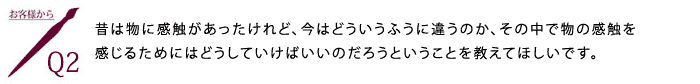
もちろん我々の周辺には大量生産される工業製品があります。手作りでその人の人格を通して背後にあった自然に、あの道具に触ることによって至っていく、そういうことは本当に少なくなってきました。でも、物を消費材として見ないという意識を持ち続けることで随分違うんじゃないかと思います。
我々はみんな、3.11を経験しました。僕は栃木に住んでいて、大きな被害はなかったんですけど、テレビでおびただしい映像を見せられた。携帯で死ぬ間際に撮っているような痛ましい画像も含めて、何度も繰り返し。それで、二つ思ったんですね。 一つは、こういう絶体絶命な時に撮れている画を、安全な場所で見ている自分は何か。つまり、これは見ていい画像かどうかということ。携帯という軽便な機械ができたことで、地震の資料としては貴重かもしれないけれど、これを見てどうするんだ、という思いがありました。気をつけないと、これはエンターテイメントになる、と思いました。
それともう一つは、繰り返しテレビが語っていた瓦礫の山。それは確かに瓦礫といえば瓦礫です。じゃあ、瓦礫っていったい何かっていうことを思ったんです。例えば、家の中にあったテーブル。そのテーブルは手作りではなくて、工業製品だったかもしれない。それが家から流されて、とんでもないところに積み上げられて、ひっくり返って傷ついて、これを瓦礫と称する。この工業製品のテーブルが瓦礫になる前にあった場所、家庭なら家庭の中にあった時、物がそこに安定してあることの豊かさを、我々は津波が来る前に知っていたか。知らないんですよね。津波が来て、瓦礫になった後じゃなくて、この物が本来あるべきところにあった時に、我々はしっかりと物を見ていたか。あるいは、物がそこにあることに喜びを、暮らしの中に持っていたか、ということを考えたんです。復興云々っていうのはもちろん色んな方法があるんでしょうけど、僕は堤防を高くすることではなくて、被災者だけではなく物と我々一人一人が出会い直す。そういうことが、こういう言い方をするとなんか偉そうに聞こえるといけないんですけど、一人一人の復興なんじゃないかと。そういうことを映画でも見続けたいと思いました。
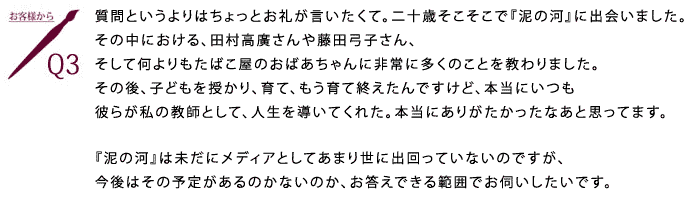
僕、この方ほんと全然知らない方ですよ(笑) だからやらせの質問じゃないんですよ(笑) 実はですね、今月の中旬に、DVDコレクションといって単品で発売が決まったんです。で、一回目が『泥の河』なんですよ。(客席拍手)書籍とDVDをセットにして販売するっていうので、『眠る男』まで一冊ずつ二ヶ月に一回くらいで出るんです。書籍のほうは批評家の前田英樹さんと僕が長い対談をしてるんです。
ついでにもう一つ宣伝してもいいですかね(笑) 今月の末に、白水社から私のエッセイ集のようなものが出ます。『FOUJITA』に関して書き下ろしたものが少し入っているんですけど、『じっとしている唄』っていうタイトルです。これ、さっきの物との関係でもあるんですけど、この言葉は陶芸家の河井寛次郎っていう人が、『六十年前の今』っていう著書に書いていた言葉で、「形はじっとしている唄 飛びながら止まっている鳥」かな。そういう文章があるんです。つまり動かない形、ものの形に、唄がある、と。そういう言葉をもらってタイトルにしました。以上、宣伝終わりです(笑)
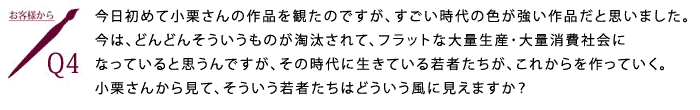
確かにフラットになってきていますね。でも、僕は逆なんじゃないのかなって思うんです。映画は生まれた時に、近代を象徴する20世紀の華として、国境を越えるユニバーサルな表現だと世界中に広まっていきました。でも、僕は映画を撮って30何年になるんですが、映画を撮ってる時に、普遍的なものなんて全然撮ってない、全部個別のものを撮っているんだと思うようになったんです。個別っていうのをもうちょっと言い換えると、全部地域的なものなんです。命があるってことはすべて地域でしかないんですよ。生まれて死んでから、みんな一つ一つの命なんですから。普遍的な命なんて無いんですよ。それを普遍的だと勘違いして、すぐに国境を越えようとしたり、情報に手を出したりして、実は我々は痩せていく。いくら工業製品に囲まれて、早い情報社会の中で生きなければいけないとはいっても、やっぱりすべては全部地域的なんだと。だから、映画も本当は一番地域を映すものだと、むしろ発想を変えていますね。若いのも年寄りのも命っていうのは全部地域にしかないということだと思います。

