

監督■ビクトル・エリセ
1940年、スペイン・バスク生まれ。スペイン内乱の余塵さめやらぬ、内戦直後の世代である。『エル・スール』のエストレリャは1957年に15歳という設定であるから、同じ世代ということになる。南に魅了される北の少女(少年)というモチーフはエリセの人生と重なりあっているのだろう。
映画学校でいくつかの習作を手がけた後、映画監督としての資格を取得したが、しばらくは映画雑誌に批評やエッセイを書きながら過ごす。
68年にオムニバス映画『挑戦(LOS DESAFIOS)』の一篇で劇監督デビュー。73年の『ミツバチのささやき』が長編映画の第一作目。約10年に1本しか撮らない、非常に寡作な監督として知られるが、そのいずれの作品も高い評価を得ている。
![]()
・挑戦 (1969)<未>
・ミツバチのささやき (1973)
・エル・スール (1982)
・マルメロの陽光 (1992)
・10ミニッツ・オールダー 人生のメビウス (2002)
スペインを代表する巨匠ビクトル・エリセの作品は、短編を除けば、『ミツバチのささやき』(73年)、『エル・スール』(83年)、『マルメロの陽光』(92年)と、たった3本の長編があるのみだ。“10年に1本の監督”などと言われることもあるけれど、最後の長編から早20年が経ってしまった。
それなのになぜ、エリセ監督は今日でも世界から称賛を受け、彼が生んだ映画は変わらず愛され続けているのだろう。いやむしろ、時が経つにつれて、作品の輝きは増すばかりだ。
今週の上映作品は、当館で3年ぶりとなる『ミツバチのささやき』と『エル・スール』。どちらも無垢な少女の成長と、彼女の周りの小さな世界を描いた物語のなかに、スペイン内戦の記憶が作品全体に影を落としている。
私たち日本人にとってはあまり馴染みのない事柄だが、スペイン映画を語る上で、スペイン内戦(1936〜1939年)の歴史は避けて通れない。最近でも、ホセ・ルイス・クエルダ監督の『蝶の舌』(99年)や、ギレルモ・デル・トロ監督『パンズ・ラビリンス』(06年)などがある。いずれも、子供の目線から内戦の暗い過去を描き出している名作だ。
『エル・スール』の中で少女エストレリャが父の乳母ミラグロスとこんな会話をする。
エストレリャ「おじい様が悪い側?」
ミラグロス「悪い側も良い側も…内戦の前の共和制の頃はおじい様が悪い側で
パパが良い側だった。フランコが勝ってから大旦那様は聖人に、パパは悪魔になった。
世の中勝った方が言い放題なのよ。」
それまで共和国政府だったスペインは、内戦によってフランコ将軍率いるファシズムが台頭し、その後36年にも及ぶ独裁政治国家となる。その間、共和派は迫害され続けた。
エリセ監督の作品に出てくる大人たちは、内戦によって傷ついた人々だ。心は空虚であり、どこか遠くを見るように生きている。彼らの目線の先にある空は、私たちが想像するようなスペインの陽気な色彩ではなく、どんよりと曇った灰色だ。
大人たちが背負った敗北感を、子供は一心に受け止める。『ミツバチのささやき』の少女アナの、あの澄んだ瞳。公民館のスクリーンの中で怪物フランケンシュタインに出会った時の、驚きと喜びに満ちた真っ直ぐな眼差しは、物語のすべてを照らしている。『エル・スール』の少女エストレリャは、沈黙を貫く父を見つめ続ける。父の心に母以外の女性がいると知っても、目を反らすことはない。過去の傷跡が癒えない大人と、未来への希望を瞳にたたえた子供。相反する彼らの姿は、内戦を体験した人々の心情を物語っている。
また、この二作で共通しているのは、子供の視点から描く“死”である。フランケンシュタインの死。負傷した兵士の死。そして、父の死。“死”は悲しいことであるが、ただ恐ろしいことだけなのではない。初めて対峙する“死”を経て、少女たちは成長する。エリセ監督の映画は、誰もが幼い頃に経験した記憶や感覚を、ゆっくりと丁寧に、けれどはっきりと呼び覚まさせてくれる。作品が持つ永遠の輝きはまさにそこにあるのだろう。
冒頭に述べたことだけれど、エリセ監督自身は“10年に1本しか撮らない”などと決めているわけでは全く無いそうだ。映画の企画やアイディアはいつでもあり、近年も精力的に活動している。ただ、映画を1本作るには、それだけの時間とお金がかかり、様々なトラブルが付きまとう、ということである。(『エル・スール』が未完の作品であるのは有名だ。エストレリャが父の故郷である南を訪ねるシーンの撮影は、金銭的に許可が下りなかった。)
だから今は、エリセ監督が次に届けてくれる新たな物語を気長に待つとしよう。静かな音に耳を澄まし、緩やかな時間の流れに身を任せ、丹念に紡ぎ上げられた名作を何度でも観ながら。
エル・スール
EL SUR
(1983年 スペイン/フランス 95分 ビスタ/MONO)
 2013年1月12日から1月18日まで上映
2013年1月12日から1月18日まで上映
■監督・脚本 ビクトル・エリセ
■原作 アデライダ・ガルシア=モラレス
■撮影 ホセ=ルイス・アルカイネ
■出演 オメロ・アントヌッティ/ソンソレス・アラングーレン/イシアル・ボリャン/ロラ・カルドナ
■1983年シカゴ国際映画祭グランプリ(ゴールド・ヒューゴー賞)
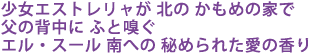
エストレリャが父アグスティンはもう帰ってこないと予感したのは15歳の時、1957年の秋の朝。枕の下に小さな丸い黒い箱、そのなかには父が愛用していた霊力で動くふりこがのこされていた。
旅に旅をかさねて、父が、北の川沿いの町で県立病院の医師として身をおちつけ、一家が郊外の一軒家に住むことになったのはエストレリャが7歳か8歳の頃。一軒家は<かもめの家>と呼ばれ、屋根の風見のかもめはいつも、南、エル・スールをさしていた。
冬の雪の日。南では雪は降らないのよと教えてくれた母の一言から、父と南の謎が幼いエストレリャの心にめばえる。祖父と大喧嘩して二度と戻らぬ決心で南を出たという父の話を母から聞かされ、エストレリャの、想像のエル・スールへの旅がはじまる――。
![]()
『ミツバチのささやき』から10年を経て、1983年に発表された長編第2作『エル・スール』。文字通り「南」を意味する題名には、切実な重さがこめられている。若い頃故郷を捨てた父の、断ち切れぬ南への思い。星と名付けられ生まれた少女が、8歳から15歳に成長し、父がなぜ南を出たか知るにつれ、次第に色濃く浮かび上がるスペイン内戦の過去。エリセは前作同様、説明的な描写はつつしみ、すべてを映像と音で詩のように描いた。
原作は、エリセ夫人のアデライダ・ガルシア=モラリスが書いた短編小説。父アグスティンを演じるのは、タヴィアーニ兄弟やアンゲロプロス監督作品でおなじみのイタリアの名優オメロ・アントヌッティ。エリセ自身が選曲した音楽も忘れ難い。テーマ曲であるパソ・ドブレ<エン・エル・ムンド>のほか、グラナドスの<スペイン舞曲集>やラヴェルやシューベルトの弦楽組曲が印象的に使われている。


ミツバチのささやき
EL ESPIRITU DE LA COLMENA
(1973年 スペイン 99分 ビスタ/MONO)
 2013年1月12日から1月18日まで上映
2013年1月12日から1月18日まで上映
■監督・原案・脚色・脚本 ビクトル・エリセ
■脚色・脚本 アンヘル・フェルナンデス=サントス
■撮影 ルイス・クアドラド
■音楽 ルイス・デ・パブロ
■出演 アナ・トレント/イサベル・テリェリア/フェルナンド・フェルナン・ゴメス
■1973年度サン・セバスチャン国際映画祭グランプリ(黄金の貝殻賞)/1973年度シカゴ国際映画祭シルヴァー・ヒューゴー賞
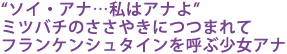
むかしむかしの1940年頃。スペイン中部のカスティーリャ高原の小さな村。アナとイサベルの幼い姉妹は公民館のスクリーンで怪物映画『フランケンシュタイン』を観ている。スクリーンのなかの少女が殺されて、フランケンシュタインも殺されて、アナは姉に聞く。なぜ殺したの? なぜ殺されたの? 姉は後で教えるといって答えない。
夜、イサベルはアナに、フランケンシュタインは怪物ではなく精霊で、死んだのではなく、村のはずれの井戸にある一軒家に生きていて“ソイ・アナ(私はアナよ)”と名乗り出れば、友達になってくれると教える。アナその話を信じた――。
![]()
スペイン内戦がフランコの勝利に集結した翌年の1940年を舞台にした、ビクトル・エリセ監督第1作『ミツバチのささやき』。撮影されたのは、フランコによる独裁政治が終了する前の1973年。スペインの作家にとって最も困難といわれたスペイン内戦の問題を深く視座に据え、繊細で詩情豊かな、単純さと美しさの極みの映画表現でやさしく語りかける。
重厚な主題を少女に託して描くのはエリセの特徴であるが、とくに本作の当時6歳の天才少女アナ・トレントの存在感は圧倒的だ。すべてを鏡のように容認するつぶらな瞳で、作品に永遠の輝きを与えている。エリセの才能とアナの魅力で『ミツバチのささやき』は世界中で絶賛された。10年に1本の寡黙な作家だが、作品はまさしく10年に1度の秀作の風格と気品が備わっている。
