
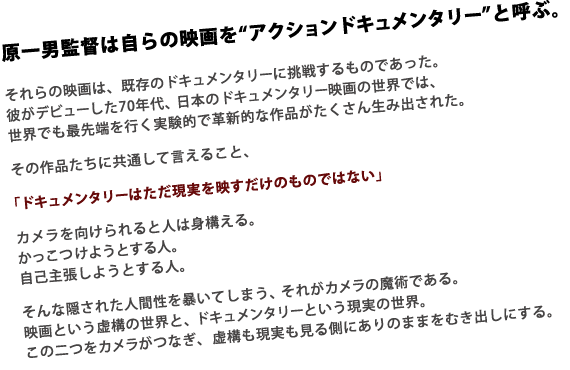
全身小説家
(1994年 日本 157分 スタンダード・MONO)
 2009年2月28日から3月6日まで上映
■監督・撮影 原一男
2009年2月28日から3月6日まで上映
■監督・撮影 原一男
■製作 小林佐智子
■編集 鍋島惇
■整音・現場録音 栗林豊彦
■出演 井上光晴/井上郁子/埴谷雄高/瀬戸内寂聴/野間宏
■日本映画監督賞/キネマ旬報ベストテン1位・監督賞/毎日映画コンクール日本映画大賞/日本映画ペンクラブベスト1位
■オフィシャルサイト http://docudocu.jp/movie.php?no=2
☆本編はカラーです
原一男監督のドキュメンタリー映画の特徴は、徹底的に一人の人間に迫るところにある。埴谷雄高に「全身小説家」と呼ばれた作家、井上光晴をこの映画は追及する。
撮影時、井上光晴は末期のガンに侵されていた。彼の闘病生活と執筆活動とのデッドヒート。それと同時に「文学によって自己の障害という 負性をプラスに転化せよ」という信念のもと、文学伝習所で文学を伝える活動もする。死を目前にしながらもほとばしる生のエネルギーには圧倒される。
 「何考えてるのか! あんたたちは!」という井上光晴の突然の怒声。持ち前の大声で楽しそうに話す姿。喜怒哀楽の激しさを感じると同時に、力強いアジテーターとしての彼を発見することができる。そして彼がこの映画を導いていることに気がつく。
「何考えてるのか! あんたたちは!」という井上光晴の突然の怒声。持ち前の大声で楽しそうに話す姿。喜怒哀楽の激しさを感じると同時に、力強いアジテーターとしての彼を発見することができる。そして彼がこの映画を導いていることに気がつく。
原一男監督はこの映画で「作家の現実から作品へと向かうプロセスを映像化したい」と考えていた。この文脈は彼自身の映画にも適用できる。そのための思考の痕跡は、映画の随所で感じられる。想像以上に早かった井上光晴の死。そのために彼の実像を三段階にして伝える方法が採用された。
・第一段階 ガンとの闘い
・第二段階 井上光晴を巡る人たちとのインタビュー
・第三段階 イメージシーン
 もしかして井上光晴がずっと生きていたら、この映画は別のものになっていたのかもしれない。こういう偶然を味方につけるための、考えながら作る独特のシステムにドキュメンタリーのおもしろさがある。
もしかして井上光晴がずっと生きていたら、この映画は別のものになっていたのかもしれない。こういう偶然を味方につけるための、考えながら作る独特のシステムにドキュメンタリーのおもしろさがある。
彼のイメージシーンを創ることによって、原一男監督は始めてフィクション劇を具体化させた。そこがこの映画の革新的なところである。一人の人生をドキュメントする中で、フィクションを発見した。そして原監督は井上光晴という『全身小説家』が、「自らの生を虚構化し、劇的に生きた人」だと気付く。この発見のプロセスは本当に感動的で見ごたえがある。

ゆきゆきて、神軍
(1987年 日本 122分 スタンダード・MONO)
 2009年2月28日から3月6日まで上映
■監督・撮影 原一男
2009年2月28日から3月6日まで上映
■監督・撮影 原一男
■製作 小林佐智子
■録音 栗林 豊彦
■編集・構成 鍋島惇
■出演 奥崎謙三
■日本映画監督協会新人賞/ベルリン映画祭カリガリ映画賞/日本映画ペンクラブベスト1位/毎日映画コンクール監督賞ほか
■オフィシャルサイト http://docudocu.jp/movie.php?no=1
☆本編はカラーです
カメラの前でかっこつけるのが井上光晴なら、カメラの前で自己主張するのが奥崎謙三である。
奥崎謙三は第二次大戦中召集され、独立工兵隊第36連隊の一兵士として、激戦地東ニューギニアへ派遣される。同部隊は敗走をかさね、飢えとマラリアと死に向かって四散していった。ジャングルの極限状態の中で生き残ったのは、同部隊千数百名のうちわずか三十数名であった。彼はその中で生き残った一人として、死んだ戦友たちのために、平和ぼけした日本社会を過激に挑発してきた。
1969年1月2日、奥崎謙三は一般参賀の皇居バルコニーに立つ天皇に向かって、戦死した友の名を叫びながら、手製ゴムパチンコでパチンコ玉4個を発射した。この事件を抜きに彼を語ることはできないだろう。
この行動が意図するものは非常に分かりやすい。そこに彼の行動の特異性を見てとることができる。彼の行動とはまず自分の主張を伝えることであった。奥崎謙三が今村昌平監督に自分の映画を撮ってくれないか、と望んでいたのは必然の結果とも言える。
 そうした経緯を経て、原一男監督が奥崎謙三を撮ることになる。その時奥崎謙三は自らを「神軍平等兵」と名乗り、神軍の旗なびくトヨタ・マークⅡに乗って日本列島を疾駆していた。そして彼が所属していた第36連隊のうちウェイク残留隊で隊長による部下射殺事件があったことを知り、真相究明にのりだす。なぜ、終戦後23日も経ってから、二人の兵士は敵前逃亡という無罪の罪で処刑されねばならなかったのか?
そうした経緯を経て、原一男監督が奥崎謙三を撮ることになる。その時奥崎謙三は自らを「神軍平等兵」と名乗り、神軍の旗なびくトヨタ・マークⅡに乗って日本列島を疾駆していた。そして彼が所属していた第36連隊のうちウェイク残留隊で隊長による部下射殺事件があったことを知り、真相究明にのりだす。なぜ、終戦後23日も経ってから、二人の兵士は敵前逃亡という無罪の罪で処刑されねばならなかったのか?
「私は、まず”戦争”をきちっとおさえたかったし、寄り道はしたくなかった。しかし奥崎はちがった。何か、コトを起こしたがっていたのだ。この奥崎と私とのズレはますます大きくなっていった」
(原一男監督の製作ノートより抜粋)
原監督が撮りたいものと奥崎謙三の行動が次第に乖離していく。その行先の分からない行程をカメラは冷静に見つめる。実はこの映画のいちばんの見どころは、そのカメラが映し出した不安感にあるのかもしれない。
戦争という現実を見つめるはずが、カメラの前で奥崎謙三が行動を起こすことによって、現実が虚構化し始める。焦点は戦争を越え、彼を突き動かす執念へと移り変わる。その変化こそがドキュメンタリーのおもしろさだ。関係の変革。虚構と現実のボーダーレス化。実は作家のメッセージ性をいちばん色濃く反映するのは、ドキュメンタリーではないかと思う。現実の中にテーマを抱え、そして見出す。原一男監督が描いたのは、一人の人間の中に存在する広大な宇宙。ぜひ早稲田松竹で味わってみてはいかがでしょうか。
(おじゃるまる)
★上映に際し、最良のプリントを用意しましたが、両作品共製作から長い年月が経っている作品のため、プリントの一部にお見苦しい箇所、お聞き苦しい箇所がございます。ご了承の上ご鑑賞いただきますようお願い申し上げます。